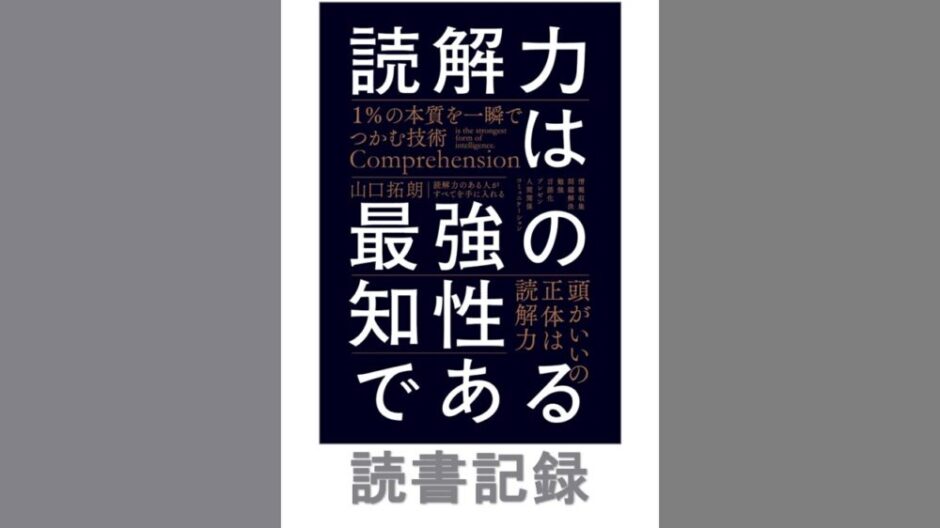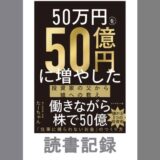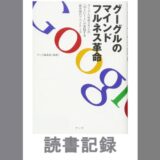Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
SNSや動画などにより、日々すさまじい量の情報を取り入れることができるようになっています。
それらの情報は猛スピードで私たちの目の前を通り過ぎていき、じっくり思考する暇がありません。
またこれらの情報収集は受動的なものになりがちです。
人によっては、長い文章を読むことが苦痛になっているかもしれません。
個人的にこれらの点に最近課題感を感じており、読書の重要性を見つめ直す機会として選んだ本です。
今回は山口 拓朗さんの著書「読解力は最強の知性である」を紹介します。
- 社会人
- 読解力に不安がある人
- 読書習慣を身に着けたい人
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
読書力は人間力そのもの
表題は本書を読んで私が感じたことになります。
本書では読解力が、ほかのあらゆる能力やスキルを総動員して使われる能力であると述べられています。
観察力、推測力、語彙力、論理的思考、批判的思考など、さまざまな能力アップに取り組んでいく必要があります。
さらに、本書でいう読解力が対象とするのは、文章だけとは限りません。
会話の内容や、対話する相手の気持ちを汲み取る力、さらには、その場の空気感、社会の潮流・潮目などを読み解くことまで含みます。
「何を」「どこまで」読み解くか
読書力は人間力そのものだという感想を持ちましたが、その中でも印象的な要素として、読解力の中に「何を」「どこまで」読み解くか、というものがあります。
これは、文章に限らず、人との会話でも重要な点です。
読解力の高い人は、人の話を聞くときも、「先を予測する」意識が強めになります。
予測が「当たる・外れる」を使って、読解の質を高めているのです。
相手の話が堂々巡りであったり、もたついたりしている場合は、「それから?」「だとすると?」「ということは?」「結局、どうなった?」などと、さり気なく続きを促す言葉をかけます。
その言葉を受けて、相手が結論や核心へと話を移していきやすくなります。
さらに、自分自身にとっても主体的・能動的に理解を進めていくことができます。
文章を読む際にも、会話をする際にも予測する習慣は、読解力そのものになります。
さらにわかりやすい例を挙げるとすれば、次の展開を予測し、ワクワクしながら推理小説を読む姿に近いかもしれません。
同じような姿勢で人の話を聞くのです。
読書力に悪影響を与える背景
現代人は、日々すさまじい量の情報に接している反面、ひとつのテーマについてじっくり思考する暇などないということを冒頭に記載しました。
スマホで提供されるコンテンツやサービスは、多くの場合、ユーザーに「思考させない」よう設計されています。
ネットフリックスのアプリを開いて表示されるおすすめのドラマのワンシーンやTickTokで流れるユーザーが興味のありそうな動画は、たくさんある選択肢の中で、ユーザーが悩んで選べない状態(選択オーバーロード)を回避するために作られた選択アーキテクチャーです。
ユーザーを動画やゲームやアプリに没頭させることで、提供企業は利益を得ることができます。
また、ウェブサイトやSNSを見ていると、ユーザー一人ひとりに最適化した関連動画や関連広告が表示されます。
最近では、識者の間で「だらだらスマホ」や「ながらスマホ」によって脳疲労が起き、認知能力──思考力や集中力、記憶力、情報処理能力など──が低下する、いわゆる「スマホ認知症」も増えてきています。
目的なくスマホを見続けることが、読解力に悪影響を与えているのです。
怖いのは、思考する機会が減れば減るほど、「ああ、こういうことね」と短絡的に決めつけたり、「どうせこういうことでしょ」と、都合よく情報を解釈したりするケースが増えることです。
思考していないため、情報のつながりを論理的に見ていく力や、論理を支える証拠や根拠を分析する力なども、当然落ちていきます。
情報を鵜呑みにすることで理解した気になっている人もいます。
 バイプロLOG
バイプロLOG