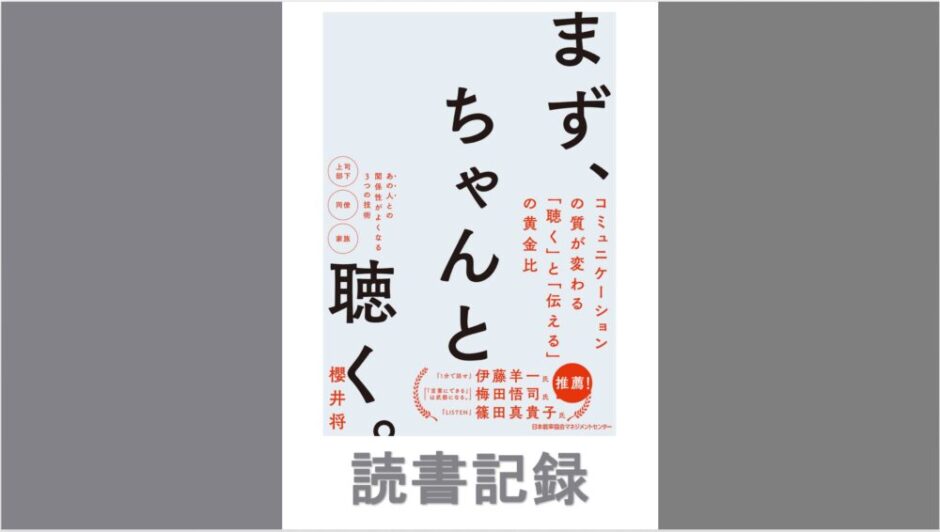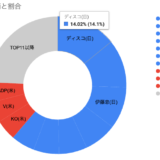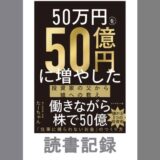Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
今回は櫻井 将さんの著書「まず、ちゃんと聴く。」を紹介します。
自分が過去に感じたコミュニケーション上の違和感が見事に言語化されていました。
特に肯定的意図の信念を持って人の話を聴くという点が心に残りました。
- マネージャー
- 他人から本音を話してもらえないと悩んでいる人
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
肯定的意図の信念を持って聴く
新人の時やマネージャーとの関係で苦しんだ時期に感じていていた違和感が初めてスッキリと言語化されていましたので取り上げました。
肯定的意図という信念があるかないかは一見分かりづらいですが、 この信念があるかないかの違いは小さいようで非常に大きいと感じました。
この信念があるかないかについては、私の経験上、話し手にとって心理的安全性が確保されているかどうかに関わるからです。
想像してみてほしいです。
聴き手が「こいつはバカだから分かっていない」「どんなに頑張ったってセンスがないから成長しない」「自分の思った通りに操ったほうが相手のためだ」というような信念を持っていたとしたらどうでしょうか。
聴くスキルが高いと、すぐには聴き手の信念は伝わってこないかもしれません。
しかし、信念は徐々に漏れ伝わってきます。
そのうちに、話し手もうっすらと気づき始めます。
私が過去に感じた、感覚的な居心地の悪さや、違和感のようなものはまさに聞き手に肯定的意図が欠如したものでした。
これは聴くスキル(「聞く」)の問題ではなく、信念(「聴く」)の問題だったのです。
スキルがあっても信念がなければ、話し手は「すごく聴いてくれているのだけど、何か嫌な感じがする」とか「言葉の上ではすごく聴いてもらえているのだけど、どこか気持ち悪さがある」など、うまくは聴いてくれるけど、ちゃんと聴いてもらっている感じが得られません。
肯定的意図の欠如が招く結果
何でも話してよい雰囲気は作っているし、部下の話を整理もしてあげている。
いつもよい課題発見や課題解決につながる話もしている。
しかし、話し手にとって肯定的意図が感じられなければ、ビジネスの問題解決ならまだしも、気持ちや感情に関わるような自分のキャリアや内面的な悩みについて相談したいとは思えないのです。
聴き手の根底に肯定的意図という信念がなければ、話し手は曖昧な話をだんだんと口に出しづらくなります。
「この人には何でも話して大丈夫だ」という気持ちが薄くなっていきます。
しかし、本書では必ずしもこの関わり方が悪いわけではないと述べています。
思考を整理して、アドバイスをもらう、うまく聴いてもらう相手としては素晴らしい役割を果たしてくれることが期待されます。
この信念は間違いなく聴く技術の土台になっており、この信念が本書のタイトルでもある「ちゃんと聴く」をつくり出すのです。
解像度を上げるために同じ言葉を使う
仕事の例で以下のような会話がありました。
部下:「前期の目標達成ができて、とても嬉しかったんです」
上司:「目標数値を越えられたことが喜びだったんだね」
この会話で何が問題になる可能性があるか、皆さんはわかりましたでしょうか?
部下は「目標達成が嬉しかった」のであって、「目標数値を越えられたのが喜びだった」ではない可能性があります。
上司が意図を持って(withジャッジメントで)聴いた結果、部下は自分の世界から意識が外れていく可能性があります。
喜びや達成感の違いをシェアしようとしていたのに、冷めてしまいます。
このwithジャッジメントで聴くのかそうでないかの違いは小さいようで非常に大きいと本書では述べられています。
そこで本書でおすすめしているのが、同じ言葉を使うというものです。
部下:「前期の目標達成ができて、とても嬉しかったんです」
上司:「おお、前期の目標達成できましたか!」
このメリットとしては、相手に話し続けてもらい、解像度を上げることができます。
相手がいる主観的な世界から、意識が抜けないようにすることが大切なのです。
肯定的意図の信念を持って子供に接する
本書では万引きを例にしていましたが、「万引きする前はどんなことを考えていたの?」「してみて、今何を考えている? どんな気持ち?」と相手が見ている景色を、横に並んで一緒に見ようとするというものでした。
幼稚園でトラブルを起こした子供の話を聞く際なども、通じる考え方だと感じました。
幼稚園でトラブルを起こした背景には、きっと何か肯定的意図があるはずだ、というあり方が子供に伝わると、「話して大丈夫かも」と思って話をしてくれる可能性が高まります。
すると、子どもの主観的世界の中での肯定的意図が見えてきます。
しかし、肯定的意図があることと、万引きや相手に怪我をさせる行為を肯定することは同義ではありませんので、そこは切り分けて伝える必要があります。
その意図についてはwithoutジャッジメントで聴くことになりますが、後者についてはwithジャッジメントで関わることになります。
子育てでも大事な観点であると感じました。
 バイプロLOG
バイプロLOG