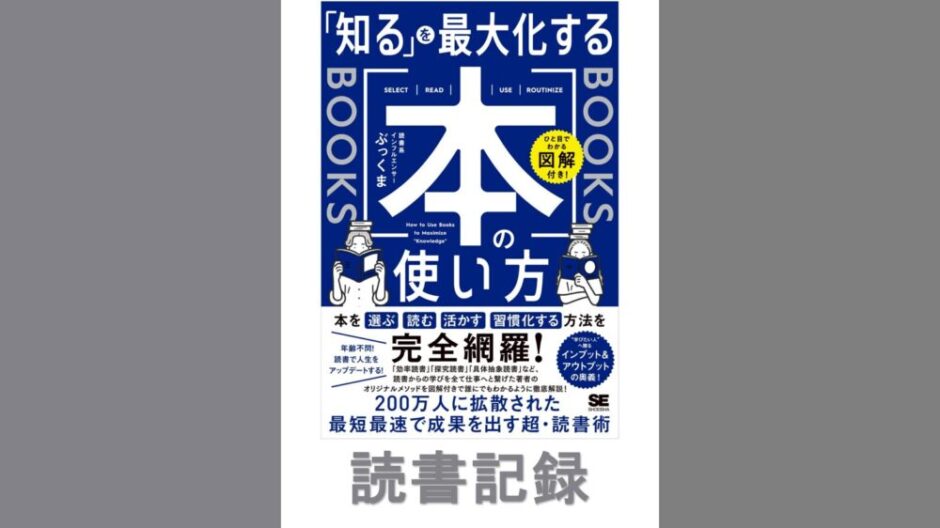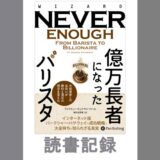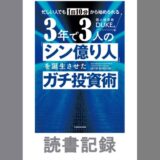Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
今回は読書系インフルエンサーであるぶっくまさんの著書「「知る」を最大化する本の使い方」を紹介します。
本は人生の武器になります。
本書は、普段から読書に関する悩みを抱えている方、プロの読書術がマネできずに挫折してしまった方、職場でステップアップを目指す方、自分に合った本を選びたい方、そして誰にもできる読書術を知りたい方に向けて書かれた本です。
本書はイラストや図解がたくさん盛り込まれており、読書が苦手な人でも読みやすくなっています。
- 普段から読書に関する悩みを抱えている方
- プロの読書術がマネできずに挫折してしまった方
- 職場でステップアップを目指す方
- 自分に合った本を選びたい方
- 誰にもできる読書術を知りたい方
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
この記事では個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけを断片的に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
経験と関連付ける
本書では広く深く読む「探求読書」の技法として紹介されていたものですが、自身の経験と関連付けて読むというのが参考になりました。
具体的には学んだことに対して次の質問をしてみることを本書ではおすすめしています。
- 同じような経験を自分はしていたか?
- 自分だったらどう考える/行動するか?
- 過去に読んだ本の内容と近い部分はあるか?
- 身の回りで同じようなことが起きたことはあるか?
私自身も特に自己啓発書では自分の経験と関連付けられるかどうかで、読んだ内容の記憶の定着度や納得感が異なっていたことを実感しています。
むしろ、私の場合は、自分の経験をうまく言語化したり、一般化してくれた本に対して、強く印象に残っているケースが多いように感じます。
逆に、経験のないこと、実感がないことは中々自分ごと化できませんので単なる情報収集になってしまいがちです。
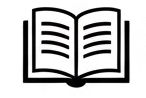
本書では、読書アウトプットの一環として読書ノートをつけることをおすすめしています。
その中で、本に合った学びとそれに対する自分の気づきやTODOを書いていくことをおすすめしています。
このときのポイントは自分ごとにすることです。
経験や出来事を思い出し、当てはめた内容を書いていきます。
アウトプットの前に自分というフィルターを通せば、本の内容をそのまま書き出すよりも、高い効果が見込めます。
気づきは学びを促し、TODOは実践への手助けになるのです。
気づきを書くのが苦手な人は自分に対して次の質問をしながら読みます。
- 重要だと思った箇所は? その理由は?
- 心に残った言葉はなに? そのときの感情は?
- 共感できた箇所は? その理由は?
- 明日からどう自分の行動に変えるか?
紙 vs 電子の読書ノート
本書ではアウトプットの一環として読書ノートをつけることをおすすめしていますが、紙と電子の違いについてまとめられています。
ちなみに、私の場合は、検索機能重視でこのブログに転記する際も便利ですので電子の読書ノート派です。
電子書籍で読む場合も多く、マーカーを引いた箇所をコピーして、読書ノートに貼り付けてメモすることも多いですので、電子の読書ノートは電子書籍との相性も良いです。
一方で、たまに図にしてまとめたいこともありますが、その場合は紙の読書ノートの方が便利な印象です。
▶紙の読書ノートを使う場合に知っておきたい特徴
- 直感的に書き込みができる
- 電子よりも記憶しやすい
- 後で見たときにどこにあるかわからない
- 携帯性が低い

▶電子の読書ノートを使う場合に知っておきたい特徴
- 検索機能により後でアクセスしやすい
- いつでもどこでも持ち歩ける
- 複数端末で書き込みできる
- ブログやSNSで発信するときにコピーできる
- 直感的な入力が難しい
- 紙に比べて記憶に残りづらい
後でアクセスしやすさを重視するなら電子。学んでいる瞬間を重視するなら、紙です。
 バイプロLOG
バイプロLOG