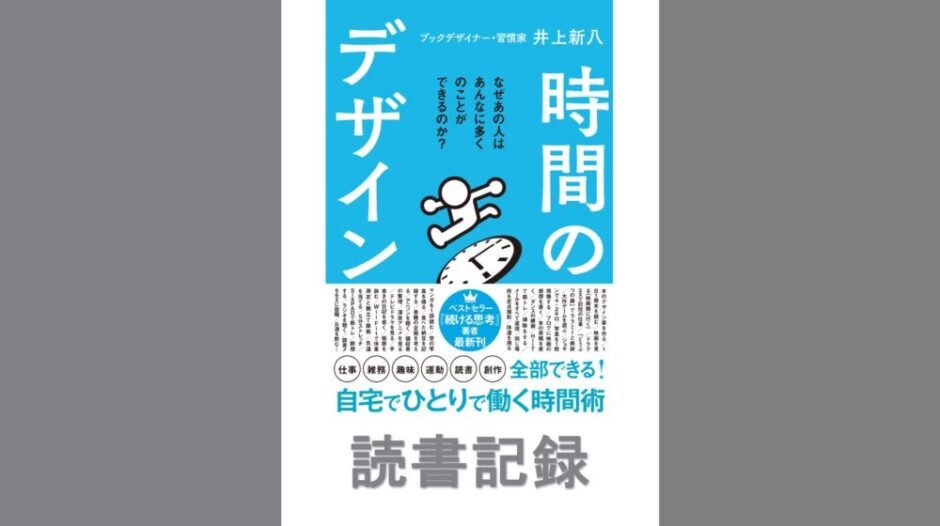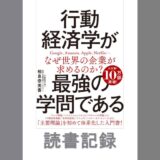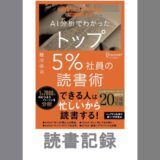Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
「時間がない」となげいている人に向けてこの本は「時間の生み出し方」を伝える本です。
そのためには仕事だけではなく趣味、運動、家事、勉強、創作活動など人生にとって必要な行動すべてを、「習慣(ルーティーン) 化」することを本書は提案しています。
今回はブックデザイナー・習慣家の井上 新八さんの著書、「時間のデザイン」を紹介します。
- 時間がない人
- 時間を生み出したい人
- 習慣化を成功させたい人
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
「やる」「やらない」の選択肢をなくしてルール化
私自身はこれまで習慣化に関する書籍をいくつか読んできましたが、以下の書籍では習慣化を成功させるために、プロセスの始まりを儀式化することが述べられています。
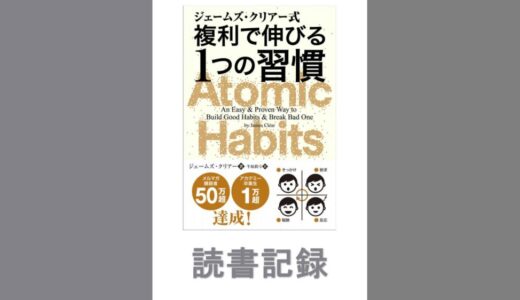 ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣|ジェームズ・クリアー 著
ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣|ジェームズ・クリアー 著
また以下の書籍においても「AをしたらBをする」というような、トリガーとアンカーを設定することが、習慣化を成功させる方法の一つとして紹介されています。
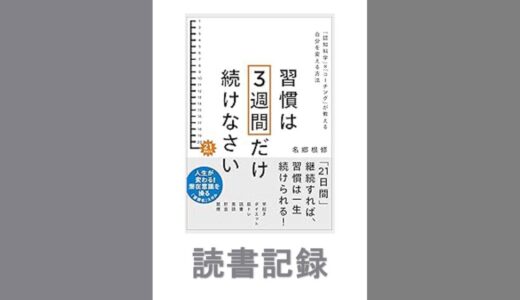 習慣は3週間だけ続けなさい|名郷根 修 著
習慣は3週間だけ続けなさい|名郷根 修 著
著者の場合、朝起きたら、「どうぶつの森」をする。
「どうぶつの森」で「花の水やりを終えたら、日記を書く」というように「どうぶつの森」と「日記」をセットにすることでアクションを自動化して「時間をデザイン」していました。
このメリットは何かをはじめることに対して「やる気」が必要がないことです。
朝起きて「どうぶつの森」で遊ぶだけで流れが生まれ、その流れにのってステップを踏むだけで、自動的に仕事がはじまります。
この「セット」が出来上がると、しばらくして、あとから新たな習慣を付け足していくことによって、どんなことでも続けられてしまうということにも気がついたそうです。
次々と行動を継ぎ足していくことで、「時間のデザイン」はどんどん進化していきました。
以下の行動経済学の考え方を取り入れると、脳はエネルギーを節約する傾向にあります。
注意深く考える・分析するといった時間をかける判断を司るシステム2を使うのではなく、脳が自動的に処理をするシステム1(直感的で瞬間的な判断に使う)を使い、行動に移せるようにすることで習慣化を成功させることができるのではないかと感じました。
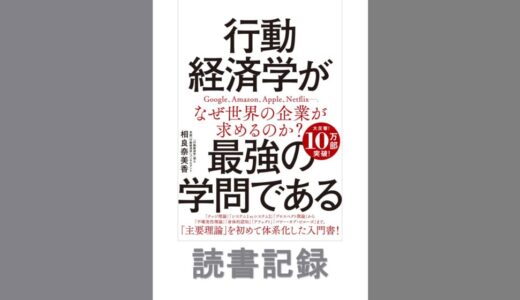 行動経済学が最強の学問である|相良 奈美 著
行動経済学が最強の学問である|相良 奈美 著
なにか行動をするのにいちばん大変なのは「やる気」を出すことだと本書では述べられています。
好きなときに「やる気」が出せるほど、わたしたちの意志は強くありません。
だから「やる気」には一切頼らないのです。
むしろ「やる気」なんかはじめから「ない」と考えて、すべて「勝手にはじまる」ようにします。
そのための仕組みが「習慣化」なのです。
習慣化とはつまり「なに」を「いつ」「どのくらい」やるかを設定する「ルール化」と言えます。
ルールを決めて作った「小さな習慣」をつなぎ合わせていくことで、時間を生み出すことができます。
一歩前進する内容を即返信
著者の場合、メールを受信しても「受け取りました。 確認します」というメールは送らないそうです。
理由は、手順がひとつ増えるだけだからだそうです。
メールを受け取った次の返信は、「これから確認します」 ではなく 「確認しました!」、「これから修正します」ではなく「修正したので送ります!」にしています。
さらに、これを即返信とセットにするそうです。
個人的には非常に参考になる考え方だと感じましたが、私の働き方に照らし合わせると、全て裁量権があるフリーランスと、大企業とで違う場面もあるのではないかと感じました。
社内検討が必要な場合、とりあえず「受け取りました。 確認します」と返事をした方が良いケースもあるなと感じました。
ただ、私自身も経験があり、最悪なのが、数日経ってから、「受け取りました。 確認します」と返事されるケースです。
この場合、今、ようやく確認したの?って感じてしまいます。
依頼をしてからしばらく経って返ってくる返信ですので、「修正したので送ります!」の内容を期待していたところ、どん底に落とされた気分になります。
大企業の方でも、ご自身に裁量権のある業務も多いと思いますので、著者のメールのルールである以下を参考にしてみてください。
- 読んだら鬼速で即返信
- 一送信につき、 必ず一歩前進
朝一はゴールデンタイム
著者は朝の4時から9時くらいまでが仕事のゴールデンタイムだと思っています。
集中力も、朝の方が圧倒的に高いですし、9時ごろまでは、ほとんど誰からもメールがきません。
静寂。 クワイエットタイムです。
そのため、集中力のいる仕事や大事な作業は、すべて早朝のうちに終わらせるそうです。
確かに私も早いときは7時、普段は7時半から仕事をしているのですが、定時開始の9時頃から急に、メールやチャットが来ます。
会議も9時以降に設定されます。
9時以降に大事な作業をやろうとすると自分のペースを乱されることが多いです。
集中力のいる作業や、途中で手を止めたくない作業は朝一に終わらせようと思いました。
7時半から開始したのでは、時間が足りないことがありますので、もう少し早めようと思いました。
また、朝一にとりあえず何か仕事を始めるのではなく、朝一にやる仕事内容も厳選すべきだと感じました。
以下の書籍でも触れられていますが、集中力の高い朝のゴールデンタイムにメールチェックをするのはもったいない時間の使い方です。
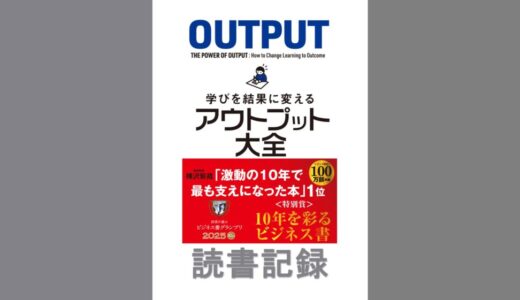 学びを結果に変えるアウトプット大全|樺沢 紫苑 著
学びを結果に変えるアウトプット大全|樺沢 紫苑 著
ちなみに、上の書籍のブックデザインはブックデザイナーの著者(井上 新八さん)が手掛けたものだそうです。
読書メモ
読書メモの残し方は、色んな本で紹介されていますが、著者の場合は以下のようなものです。
- できるだけ自分の言葉に翻訳して簡潔に書く
- 心に響いた一文はそのまま書きうつす
- 感じたことは、自分の意見だとわかるように印を付けて書く
- 「これいいな」「マネしてみようかな」と思ったことをメモする
「わーこれわかる!」とか「これとは反対のこと考えているかな」というなんでもないような感想でも読み終わると忘れていたりします。
なので、なにか心が動いたらなんでもメモしておくのは有益です。
「めちゃ共感した」くらいの何気ない感想こそが、1年くらい経ったときにその本の内容を思い出す大事なトリガーになります。
そしてメモをするだけではなく、できるだけすぐに実践するようにします。
なかなかそのままマネできそうもないものは、自分なりにその行動を「続けられそうなサイズ」にアレンジして実践します。
実際に著者が朝のルーティーンでやっていることは、本を読んで「いいな」と思ったことを自分なりにアレンジしたものが多いそうです。
メモを取るだけではなく、他の人も見られる場で、アウトプットもしています。
改めて読書をしながら書いたメモにさっと目を通し、短めの文章にまとめてXの投稿画面にペーストしています。
たいてい少し文字量がオーバーするからいらない表現を削ったり、言い方を変えてみたりしなければなりません。
字数の制限は簡潔にものを伝える訓練になります。
削るために何度もメモを読み込むので、結果として本の内容が記憶に残りやすいそうです。
 バイプロLOG
バイプロLOG