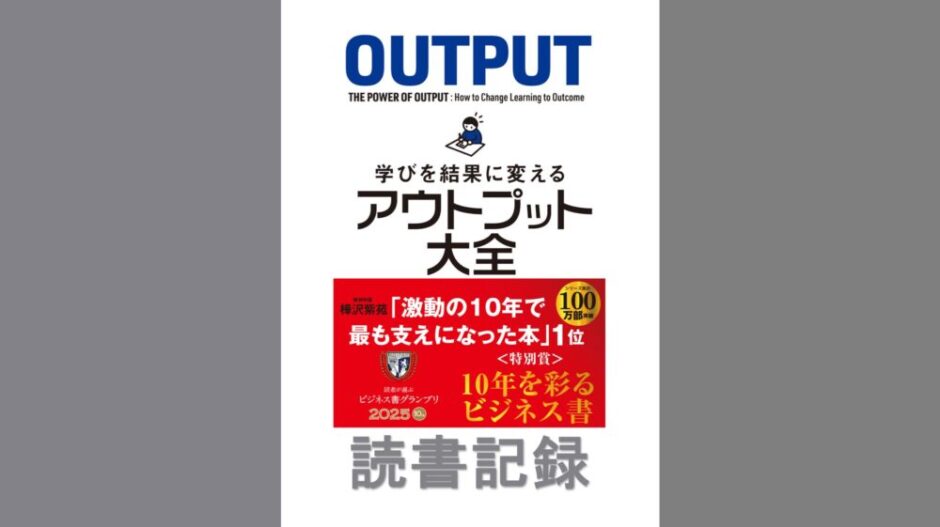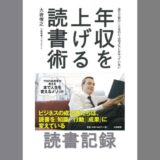Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
普段、読書が習慣化している私ですが、インプットに偏りがちで、インプットの割に、読書の内容が身についていないのではないかという課題感があり、克服をするために読みました。
今回、タイトルと目次を読んで、読破しようと思った書籍ですが、以前に読んだ以下の「読んだら忘れない読書術」と同じ著者でした。
サラリーマンにもおすすめで、日常の働き方から、自己啓発に至るまで、広い枠組みでアウトプットに関するコツが取り上げられています。
著者は10年で28冊の本を書き、メルマガを3000通以上発行し、動画を1500本以上更新するような、コンテンツ制作能力を持ち、アウトプットの達人ですが、インプットとアウトプットの黄金比率「3対7」を実現できるようになったのは、40歳を過ぎてからとのことです。
この記事を見ていただいている方が何歳かはわかりませんが、何歳から始めても決して遅すぎることはないと感じました。
今回は精神科医である樺沢 紫苑さんの著書、「学びを結果に変えるアウトプット大全」を紹介します。
- 本を「読む」だけで終わっている人
- 仕事で成果を上げたい人
- 年収を上げたい人
- 生産性を上げたい人
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
メールチェックを減らす
本書では始業直後のメール返信やメールチェックの回数が多いことを推奨していません。
始業直後のメール返信をしないことは本書を読む前から、私自身やっていたことなんですが、習慣としては悪くないことが確認できたので良かったです。
私達は、メールに振り回され、生産性を落としてしまっている側面があるのではないでしょうか?
メール対応により、1日で決めていた自分のペースも乱されることになります。
1日の中で最も集中力が高い時間帯は「朝」 です。
この朝の時間帯に、どれだけ集中力が高い仕事をこなせるかで、1日が決まります。
メールチェックというのは、休み時間にもできる 「最も集中力を必要としない仕事」のひとつです。
それを朝30分もかけて行うのは、深刻な時間損失であると本書では述べられています。
ただし、緊急のメールもありますから、メールチェックをゼロにしろとはいいませんが、 朝のメールチェックと返信は5分以内に終わらせることを推奨しています。
まずは1時間か2時間、集中して仕事をしてその後休憩がてらメールチェックをすればいいのです。
メールチェックの回数が多すぎるのも時間の無駄になります。
メール開封をしてから内容を確認し、メール返信を後回しにする人もいるでしょう。
「あとで返信」は、もう一度メールを開封して読み直す必要があるので2倍時間をとられます。
これならば、メールチェックをしないほうがましであると述べられています。
これは、私自身当てはまっていたので、働き方に取り入れようと思います。
同じメールは二度開かない。
メールを開いたら、即座に返信して完了することを習慣にしましょう。
読書であってもアウトプット量を稼ぐことを意識
これは、私自身課題意識があったので、本書を手に取るに至りました。
読書の習慣がある人でも、月何冊読んだなどインプットの量は意識しても、月何冊分アウトプットしたというところまで意識している人は少ないのではないかと思います。
読書という活動は油断していると、インプットに偏りがちです。
私も漏れなくこの例の一人でしたが、読んで満足して、間髪淹れずに、また次の本を読み始めます。
読書をする場合、インプット量を稼ぐのではなく、アウトプット量を稼ぐことを意識しなければなりません。
1冊読んだら、1冊しっかりとアウトプットということです。
アウトプットが終わるまで、次の本を読み始めるべきではないのです。
私の場合、読みたい本を数冊購入し、手元にあるケースがありますが、1冊読み終えたら、次の読みたい本を読み始めるのを我慢して、既に読んだ本のアウトプットをするという感じでしょうか。
今の私の場合、これは意識しなければできないことです。
本書では、ビジネスマンで月3冊読んで、3冊分のアウトプットができている人は、20%もいないだろうと述べられています。
「月3冊インプット、0冊アウトプット」 と 「月1冊インプット、1冊アウトプット」を比べると、「月1冊インプット、1冊アウトプット」のほうが圧倒的に成長できます。
こちらのほうが、時間も短くて済みます。
本を1冊読むのに、仮に2時間かかるとすると、1冊読むのをやめれば、2時間のアウトプット時間を捻出できます。
2時間あれば、最初に読んだ本のアウトプットをするのには、十分すぎる時間ということになります。
語学を習得する場合、インプット<アウトプットという考えは浸透している感がありますが、読書の場合も同じですが、見過ごされがちだと感じました。
インプットとアウトプットの黄金比は3対7
読書という行為はどうしてもインプットに偏りがちだという話をしました。
これを回避するために、私は読書ノートをつけ、その中でもシェアしたいものをこのブログで発信しています。
私の場合、これらを取り組んだとしても、まだアウトプットの量としては、インプット量には及んでいないのではないかという感覚があります。
本書では、多くの人が「インプット過剰/アウトプット不足」に陥っており、それこそが 「勉強しているのに成長しない」 最大の原因と述べています。
インプットとアウトプットの黄金比は、3対7だそうです。
インプット時間の2倍近くをアウトプットに費やすよう意識することを本書では勧めています。
それぐらい、我々はアウトプットを意識したほうが良いということですね。
「想定問答集」「Q&A集」を作る
本書でおすすめしている、「想定問答集」「Q&A集」をつくるというのは、過去、私自身が大事なプレゼンに備えて実施して良かったと感じたものになります。
しかし、普段は手間でサボり気味だったので改めて意識しようと思いました。
「想定問答集」「Q&A集」をつくることで会議で出そうな質問に対して、事前に文章でまとめ、質問が出ても、瞬時に適切な回答ができます。
何問くらいの「想定問答集」をつくるべきかという問いに対しては、「10-30-100の法則」を取り上げています。
これは著者の数百回を超える講演、セミナーの質疑応答、議論から導かれた経験的法則ですが、70%をカバーする10問、 90%までカバーする30問、99%をカバーする100問を作っておくイメージです。
自分で質問を書き出し、それに対する答えを10問準備します。
10問ぐらいならできそうですね。
それでも不安な人は、30問、さらには念には念をで100問準備します。
議論が苦手な人、瞬発的に適切なQ&A対応ができない人は事前の準備でカバーをします。
本書では不思議なことに、議論が苦手な人ほど事前の準備せず、議論が得意な人ほど、 資料やデータを用意すると書かれています。
「議論が上手」「話し方が上手」 かどうかよりも、どれだけ事前に周到に準備するかで結果が決まります。
議論の流れを予測し、 徹底抗戦できる武器、資料やデータを十分に備えておけばいいのです。
 バイプロLOG
バイプロLOG