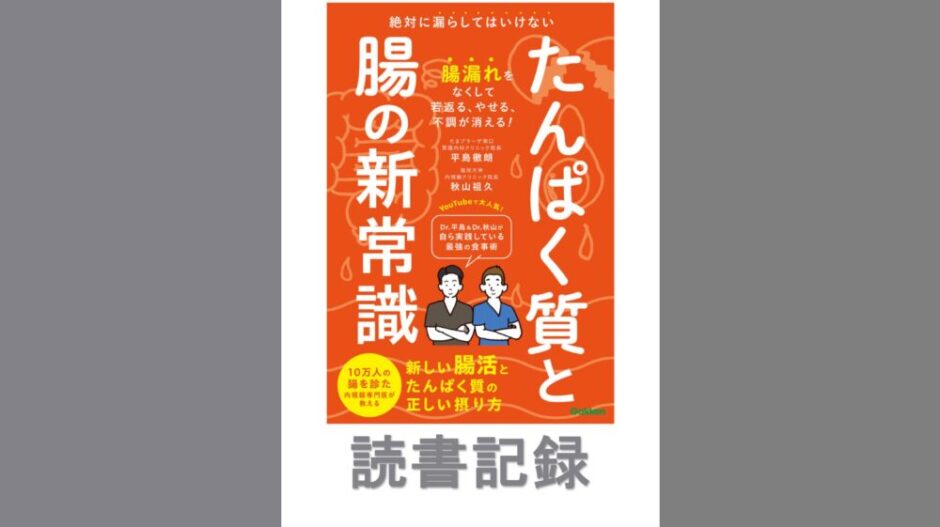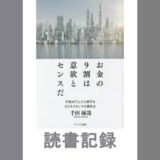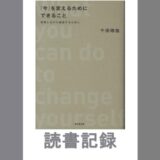Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
私自身は日常で意識してたんぱく質を取り入れるようにしています。
また、ファスティング関連の書籍を読んでいると、本書でも記載があった、腸は「免疫の要」であることや、意識的に空腹の時間を作ることでオートファジーを発動させる話なども再確認することができました。
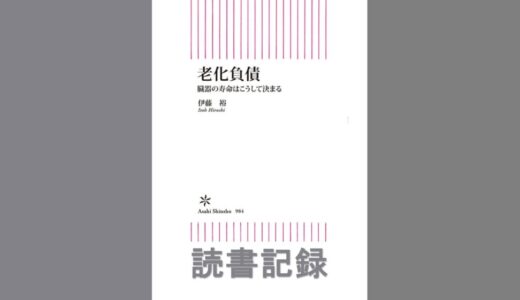 老化負債 臓器の寿命はこうして決まる|伊藤 裕 著
老化負債 臓器の寿命はこうして決まる|伊藤 裕 著
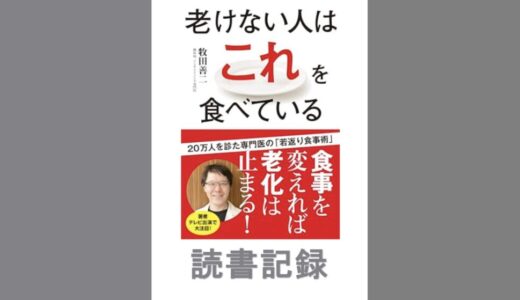 老けない人はこれを食べている|牧田 善二 著
老けない人はこれを食べている|牧田 善二 著
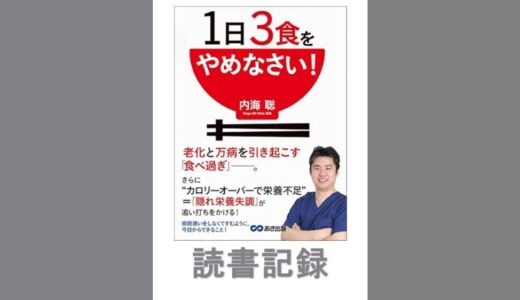 1日3食をやめなさい!|内海 聡 著
1日3食をやめなさい!|内海 聡 著
本書ではタンパク質が日本人に不足しがちな点や、たんぱく質不足を回避する食事、不要なものが腸から漏れ出して吸収され、そのぶん摂ったはずの栄養素が正しく吸収されていない「腸漏れ」(リーキーガット症候群)についても新たに知ることができました。
今回は平島徹朗さん、秋山祖久さんの著書、「たんぱく質と腸の新常識」について紹介します。
- ストレスを抱えている人
- お酒をたくさん飲む人
- ときどき甘いものを爆食いする人
- 毎日パンやパスタやうどんなどの小麦粉食品を食べる人
- チーズやヨーグルトは欠かせない人
- 忙しくて合成添加物たっぷりの加工食品を毎日のように食べる人
- 睡眠不足の人
- 上記のうちどれかひとつでも習慣化しているなら、腸漏れしている可能性がありますので本書を一読することをおすすめします
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
腸は免疫の要
本書を通じて腸は私が想像していた以上に重要な器官だったという感想を持ちましたので紹介します。
腸は体内に栄養を取り込む「吸収の要」であるという印象を持っている方は多いと思います。
この認識自体は間違いないのですが、腸にはさらに、ウイルスや細菌、有害物質といった悪いものをブロックする「免疫の要」でもあるようです。
というのも腸内には体内の免疫細胞の70%が集まっているようです。
腸は、体にいいものと悪いものを選別している大事な器官でもあるのです。
腸と認知症の関係
認知症は「脳のゴミ」と呼ばれているアミロイド βが原因物質で、これが脳に溜まることで起こります。
アルツハイマー型認知症研究の第一人者であるデール・ブレデセン博士は、アミロイド βは脳が何らかのダメージを受けたときに発生することを突き止めました。
その主なダメージの要因というのが、次の3つになります。
①炎症
②栄養不足
③毒素
これらはすべて、腸に関係することが分かります。
かつては脳が心身の最高司令塔だと考えられていました。
しかし、近年では、腸から脳に送られる情報のほうが多いことが判明しているようです。
そして、この脳への情報発信に大きく関係しているのが腸内細菌であることも明らかになってきました。
つまり、「腸・腸内細菌・脳相関」ともいえる仕組みがあることがわかってきたのです。
そのため近年では、腸内細菌と認知症の関係にも注目が集まり、腸内環境をよくすることで認知症を予防できる、改善できることがわかりました。
オートファジーによって認知症予防
空腹の時間を作ることにより飢餓の気配を察知した脳は、体内の脂肪を利用して「ケトン体」というエネルギー源をつくり出して蓄えます。
そして、細胞は自らを分解、新生して自浄する「オートファジー」というシステムを発動させます。
オートファジーが発動すると細胞のターンオーバーが促進され、摂り入れたたんぱく質が有効に使われます。
ここでも腸から脳への情報発信があるように感じました。
「ケトフレックス12/3」と呼ばれるものは認知症予防に取り入れられています。
「ケトフレックス12/3」は「1日のうちで12時間断食し、さらに就寝の3時間前までに夕食を済ませる」というルールになっています。
「ケトフレックス12/3」により前述のようにオートファジーを発動させ、「脳内のゴミ」である、アミロイドβを減少させ、認知症を予防します。
タンパク質は食べ溜めができない
細胞のターンオーバーはたんぱく質不足が続くと、その周期が乱れ、細胞は老化します。
それは体の機能低下や不調の原因にもなります。
つまり、十分なたんぱく質をとることによって、ターンオーバー後の体を若々しく作り替えることができます。
ターンオーバーの周期は臓器や組織によって異なり、それぞれ以下の期間で新しい細胞に生まれ変わります。
胃・小腸の粘膜:約3日
大腸の粘膜:約10日
皮膚・肝臓・腎臓:約1カ月
筋肉:約2カ月
血液:約4カ月
骨:約5カ月
半年後の自分の体における上記の臓器や組織は今の自分のものと違うと考えると何か不思議な感じがします。
ターンオーバーには十分なたんぱく質が必要なのですが、ここで問題があります。
たんぱく質は食べ溜めができません。
1食でまとめてたんぱく質を摂ったとしても、体が一度に利用できるたんぱく質の量には制限があります。
1食あたり20~30g、多くても30~40gが一度に利用できるたんぱく質量といわれています。
そのため、たんぱく質の摂取量を大幅に増やしたい場合は、1日3食だけでなく間食を活用して、たんぱく質を摂取する回数を増やす必要があります。
 バイプロLOG
バイプロLOG