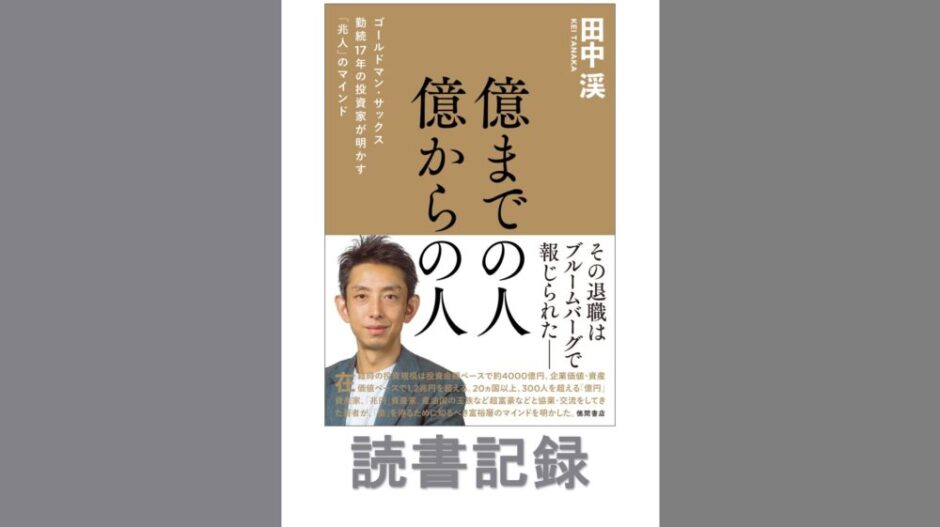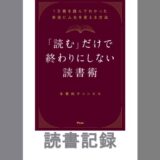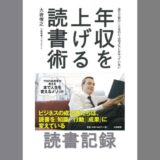Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
pivotの対談で興味を持って、読んだ本です。
富裕層の哲学や思考、習慣など、彼らの生態知り、自分も近づきたいと思い、購入に至りました。
富裕層マインドにシフトする事で「億を超える人」になれる可能性があります。
人は想像ができないことはできませんし、想像できない人にもなれません。
本書を読む意義は、本書を通じて、富裕層についてイメージを持てるようにして、行動につなげることです。
今回は、田中 渓さんの著書、「億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド」を紹介します。
- 富裕層になりたい人
- 富裕層の哲学や思考、習慣などを知り、取り入れたい人
本を読んだ感想ですが、億からの人というのは何かとんでもない特別なことを日常に取り入れている、超人のような雲の上の存在というわけではありません。
1日だけでは我々でもできるような小さな努力を積み重ねてきた人のように感じました。
ただ、小さな努力であっても、積み重ねることによってとんでもない所にたどり着いている人たちです。
日々積み上げたものは、1日1日は小さなものであっても、億までの人には取り返すことができないほどの差になっており、その差は、広がる一方なのではないかと感じました。
億からの人は小さな努力を積み重ねることが習慣化されているからです。
仕事でもプライベートでも、何かひとつのことを「習慣化」できる力を身につけておくとが鍵のように感じました。
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
凡人が100万人に1人の非凡になる戦略
大谷翔平選手のように、ひとつの道で100万人に1人の存在になるのは1万時間の努力だけでは必ずしも辿りつけません。
そこは、ある程度才能の域に入ってしまうことが想像できますし、大谷選手のように才能もある人が努力もできるとなると、凡人にはとても太刀打ちできません。
ただ、1000時間の努力で100人に1人の存在くらいにはなれます。
これを2つ掛け合わせれば、100×100で1万人に1人の存在、3つ掛け合わせれば、100×100×100で100万人に1人の存在になれます。
これは専門性が異なる様々な職場を経験してきた私も心当たりがあります。
過去の職場で、専門性では1番ではなかったですが、職場が変わり、新しい専門性と過去の専門性を掛け合わせなければならない場面になると、一気に貴重な存在になります。
凡人でも専門性の掛け合わせによって、課題を解決できる存在になれば、非凡な存在になれるのです。
メールの返信やアウトプットが速い
特にビジネスシーンでのメールやチャットの返信の速さは、他人に対して気になることが多いですし、私自身忙しい時など特に気をつけようと思いました。
特に取り入れようと思ったのが、時間をかけて丁寧な返信をするより、とりあえず「拝受しました」「のちほど改めて」のように、まずは何かしらのレスポンスを出すということです。
送り主はいつでも相手の反応を気にしています。
何かしらのレスポンスがなけれれば、届いているのかどうか、見てもらえているのかどうか、リマインドしたほうがいいのかなど不安になります。
たとえ、あなたが依頼事項に取り組んでいる最中で、完了後レスポンスをするつもりであったとしてもです。
何かしらのレスポンスをすることで、相手は「読んで意識してくれているのだな」と、モヤモヤがなくなります。
「スピード感 ×相手の心情を察して動く」は基本であると本書では述べられています。
チームの稼働率を100%にできる
これはあなたが経営者であっても、ある会社のマネージャーであっても、部下の立場であっても共通することだと感じました。
経営者であれば、社員の稼働率を100%に、マネージャーであれば部下の稼働率を100%に、部下の立場であれば、上司であるマネージャー、同僚も含めて、全員の稼働率を100%にします。
テキパキと役割分担とデッドラインを明確に決めて指示をする、作業の山場が来る日のことを先読みして、各人のスケジュールをあらかじめ押さえておくなどが必要になります。
会社であっても、部署であっても、自分の担当業務であっても、使えるリソースの稼働率を上げることによって、生み出す価値を高めることができます。
判断事項は、考えなしに持ち帰らず、その場で結論を出す
たとえあなたの一存では決められないことであっても、表題のことを意識します。
本書の例を借りると
「・・・リスクは ~にあるが、 ~の理由でリスクは限定的だと社内整理できると思う。それらを踏まえて、このリターンが出るのであれば、私の経験上、社内稟議を通せる可能性は高いと思うので、ぜひ取り組みたい。戻り次第至急マネージャーと議論し、今日中に連絡する。社としての最終判断には 2週間時間をいただきたい」
という具合で、その場での仮説、結論を出したうえで、意思決定権者の判断を仰ぐために「持ち帰る」という対応をとります。
相手もこの人と話しても無駄だという印象や、頼りない印象を受けず安心感がありますよね。
相手の立場も理解し、責任感とオーナーシップを持つことが重要です。
デッドラインの半分の時間で8割のものを出す(80/20の法則)
日々の仕事でも、全体の8割の準備が済んだら、残りの2割を仕上げて10割にしてから次の段階に駒を進めるのではなく、 8割の状態で次に行こうと決め、まず先に進めることを優先していきます。
2割のものを10割にする作業は、 8割の時間がかかることも多い(80/20の法則)ため、スピード感を優先して見切り発車で進めていきます。
しかも、8割のものはデッドラインの半分の時間で出します。
デッドラインの半分の時間で出すためには、要所要所で大幅な軌道修正リスクを排除します。
あれこれ悩みながら、最後まで作業して、一発勝負するのではなく、早く出して、軌道修正リスクを早い段階から排除する働き方を意識するようになってから、私自身、成果が上がるようになりました。
ただ、最初は8割の状態で出すということに不安や抵抗を感じるかもしれません。
私もそうでした。
ただ、ただ残り2割は8割の時間がかかる、細かい点だったりするので、やはり8割の状態で早く出したほうが良いと今は思っています。
本書の例では、「まだ粗いのですが」「 3割くらいの仕上がりですが」などと期待値を下げながら、その都度さりげなく方向性を確認して「期待値コントロール」「満足度コントロール」するテクニックが紹介されています。
富裕層は、意思決定を他人に委ねない
これはあなたがどのような立場であってもというところがポイントではないでしょうか。
会社員だから自分で決める仕事や権限がない思われるかもしれません。
でも会社員であっても以下のような小さなことに意思決定はできるはずです。
「出勤前の30分は自分のための勉強の時間投資と決める」
「締め切りのある仕事では、自主的に『締め切りの8割の時間で必ず提出する』と決める」
「大事な決め事の会議に参加させてもらうよう働きかけ、そこで必ず発言する」
意思決定を間違ってしまうという人もいるでしょう。
そのような人であっても、失敗の積み重ねで判断の精度を上げていけばいいのです。
間違えたら軌道修正をすれば、その分学習し、経験値を積んだだけ成長も見込めます。
本書では、「遅い意思決定をした結果、正しい」ことよりも、「速く意思決定した結果、間違っていた」ことの方が価値があるとしています。
経験を増やすために「今すぐ」「少額から」はじめる
最後に、本書で印象に残った投資に関する内容について紹介します。
株式投資をしていると、投資は元本割れのリスクもありますので余裕資金でということを聞くことがあるかもしれません。
当然、余裕資金ということになると、まとまったお金が貯まってからという考えになる人もいるかと思いますが、本書では「今すぐ」「少額から」始めることをおすすめしています。
最大のメリットは経験値を増やせる点です。
勝つことも負けることもあるのが投資の世界です。
投資初心者にとって勝ち負けより大切なのが経験値を上げていくことです。
個人的には、インデックス投資だけではなく個別株投資もおすすめです。
インデックス投信は積み立てて放置するだけなので、あまり教訓は得られません。
セクターを分散して個別株を保有していると、セクターローテーションがあることが肌で感じられます。
インデックスでは経験できないような1日の下落も経験しますので、自分のリスク許容度も分かってきます。
財務諸表や決算、企業のビジネスモデルにも興味を持ち始めます。
私の場合、インデックス投資では得られない経験や、視野の広がりがありましたのでおすすめしています。
これらの経験を、極端な話、まとまった退職金や相続があってから初めて経験すると目も当てられないような状況になりかねませんので、手元資金が少ないうちから経験しておいたほうが良いと考えています。
 バイプロLOG
バイプロLOG