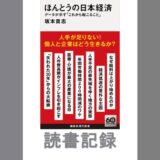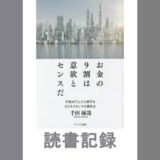Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
Pivotの対談で興味を持ちました。
センスや感覚、経験に頼り、なんとなくマネジメントするのではなく、型を身につけるということについて体系的に解説されている点に興味を持ちました。
古い時代に自分が受けてきたマネジメントは感覚的には、時代にそぐわないですし、あまり参考にならないはずです。
今から振り返るとマネジメントと言えたのかどうかも怪しいです。
マネジメントの型について体系的に身につけようと思い、読みました。
今回は長村 禎庸さんの著書「急成長を導くマネージャーの型」を紹介します。
- ベンチャー企業のマネージャー
- マネージャー
本書は著者の経験から、タイトルにもある通り、急成長を目指すベンチャーのマネジメントについて中心に解説されています。
ベンチャーのマネージャーは人もたくさんいるわけではないので経営陣の一員という側面があり、会社への影響度は大きいという点が、大企業の中間管理職との違いになります。
しかし、読んでみた感想としては、大企業のマネージャーも参考にできる部分があると思いました。
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
メンバーの能力評価・バリュー評価に関する「事実」を毎日ストック
会社により評価制度は異なりますが、評価軸としては概ね次の3つに収斂されるのではないでしょうか?
・成果(定量あるいは定性で、評価期間の目標が達成できたかどうか)
・能力(どういう能力を身に付けたか)
・バリュー(自社で定めるバリューをどう体現したのか)
成果についてはわかりやすいですが、能力評価・バリュー評価については、観察した事実を元にフィードバックをしなければ、メンバーには受け入れられません。
そこで、著者はメンバーの能力評価・バリュー評価に関する「事実」を毎日ストックすることを推奨しています。
気持ちが折れてしまうので、毎日1人あたり1~3分程度のメモで構わないと記載されています。
これが数か月分溜まれば、事実に基づいた非常に有効なフィードバックができます。
評価活動は最優先事項
メンバーの能力評価・バリュー評価に関する「事実」を毎日ストックするというのはメモ程度であっても、大変な作業です。
しかし、評価に向き合うという仕事は、マネージャーにとって最優先であると述べられています。
「忙しくてここまでできない」というなら、ほかの仕事を削ってでも、評価を最優先すべき書かれています。
だれしも、きちんとだれかが見てくれているからがんばることができます。
自分ががんばった結果をだれかに見てもらい、それに対するリアクションが欲しいのです。
だれも見てくれていない仕事ほど、寂しくてやりがいのないものはありません。
チームの目標達成にとって、評価活動は遠回りなようで、一番重要な業務なのです。
メンバーごとに、さらには業務ごとに、関わり方を設計
最後に本書の中で一番印象に残った箇所を紹介します。
あなたは「マイクロマネジメント派」か?「放任派」か?そんなことを考えたり、議論することは無意味です。
マネージャーはメンバーごとに、さらには業務ごとに、関わり方を設計しなければなりません。
メンバーのスキルと業務の重要度で仕事をラベルづけし、そのラベルに応じて関与の方法を変えるのです。
具体的には以下のように業務の重要度とメンバーのスキルを4象限に分けます。
| ③ メンバーのスキル:低 業務の重要度:高 関与の方法:共同ワーク | ① メンバーのスキル:高 業務の重要度:高 関与の方法:定点確認 |
| ④ メンバーのスキル:低 業務の重要度:低 関与の方法:育成 | ② メンバーのスキル:高 業務の重要度:低 関与の方法:お任せ |
象限①に対しては、メンバーのスキルが十分なので基本は任せますが、重要度が高いので定例MTGなどを開催し、定期的に報告をもらうことで状況確認をします。
象限②に対しては、メンバーのスキルが十分で、かつ重要度も低いので基本お任せで問題ありません。
この業務に関しては、チャットなど、ライトな形で報告を受け取るのみでOKです。
象限③に対しては、メンバーのスキルが不十分で、かつ重要度が高いことから、マネージャーが深くメンバーに関与する必要があります。
少なくとも、私の周囲ではここができていないマネージャーがこれまでは多かったですので、これができる数少ないマネージャーは印象に残っています。
大企業とベンチャーの違いもあるのかもしれませんが。
ここではMTGを頻度高く開催してアドバイスをしたり、場合によっては一緒に手を動かして業務に臨みます。
育成目標をもって計画的にメンバーを育成を行う場合、象限④で行います。
なぜなら、共同ワークゾーン(③)では、業務の重要度が高いので途中でメンバーの仕事を奪ってしまうことになり、計画的に育成できないからです。
私自身のことを振り返ると、貴重な経験をさせてあげたいと思い、③で育成を試みたことがありましたが、まさに本書で記載されていた通り、重要度の高さから途中で自分で引き取り、育成が中途半端になってしまった経験がありました。
全体を通して私自身、メンバーの動きが見えなくて不安になることや、会話ができていなくて不安になることがありました。
これはメンバー&業務において必要な関与度が言語化されていないことが原因でした。
必要な関与度が整理されていないと、漠然とした不安からメンバーに無用な関与を増やすなど、関与方法を誤るリスクがあるのです。
 バイプロLOG
バイプロLOG