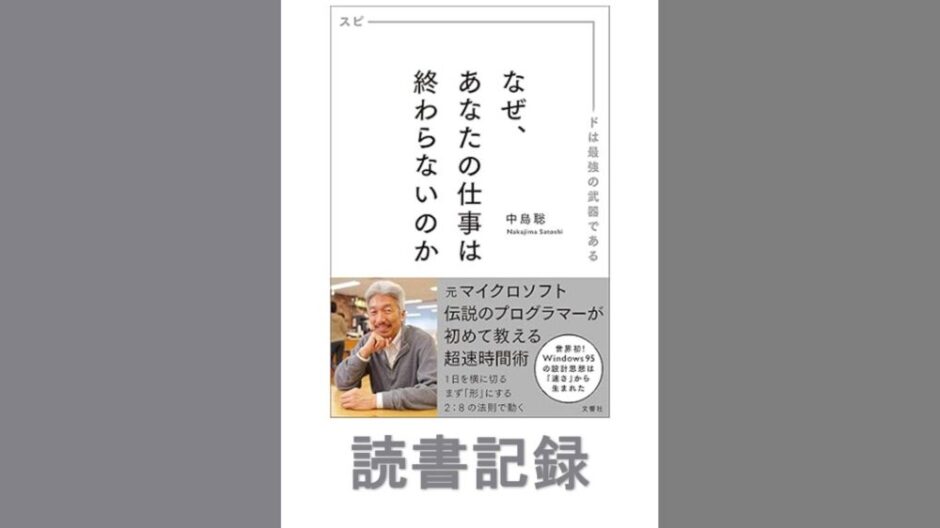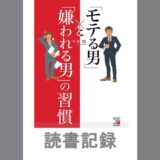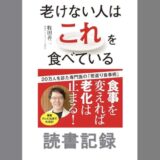Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
個人的に最近、残業が多く、仕事を抱えがちであるため、自分の働き方を見直すためにも読もうと思った本です。
著者の中島聡さんはマイクロソフト日本法人、マイクロソフト米国法人出身で、Windows95のOS開発に携わった人です。
現在の「右クリック」や「ドラッグ&ドロップ」の概念を作った人です。
著者自身の人生の話が具体的に取り上げられており、本書で取り上げられている教訓についても心当たりのあるものが多くありました。
今回は中島 聡さんの著書、「なぜ、あなたの仕事は終わらないのか」を紹介します。
- 仕事が多く絶望している人
- 仕事に追われ、家族との時間や勉強する時間などのプライベートが確保できない人
- 集中が切れやすい人
- 一流のビジネスパーソンの時間の使い方を学びたい人
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、単なる要約になるとネタバレになりますので、詳細は書籍を購入して確認してください。
完璧を求めすぎず早く形にしたものを出す
私も仕事柄、新しい企画を提案することが多いのですが、時間をかけて完璧を求めすぎず、早く形にすることが重要であると感じる場面が多いです。
経験上、早く出すことで、例えば「企画を考えて」と言ってきた上司と早い段階で方向性が合っているかどうかの感触や反応を確認することができます。
そして何よりも、その後の改善期間を長くとることができます。
長めに確保できた改善期間を使い、自分が持っていない知見を持っている人の意見を取り入れたり、違った目線の意見を取り入れることもできます。
壁打ちをする時間を長く確保できることで、最終成果物はより洗練されたものになります。
本書の例えを借りると、延々とアップデートを繰り返しているスマホアプリのような進め方になります。
100点の仕事など存在しません。
それよりも最速でいったん形にしてしまってから、余った時間でゆっくりと100点を目指して改良を続けるのが正しいと述べられています。
また、本書で述べられていた、どんなに頑張って100%のものを作っても、振り返ればそれは100%ではなく90%や80%のものに見えてしまう(100%のものは、そんなに簡単に作れるものではない)というのも、普段仕事をしていてすごく感じます。
最初から100%の仕事をしようとしても、ほぼ間違いなく徒労に終わるなら、早く形にして、壁打ちをして100%に近づけた方が良いと感じています。
似たような概念は、以下の書籍にて80/20の法則として紹介されていました。
最後の2割のものを10割にする作業は、 8割の時間がかかることも多いため、スピード感を優先して8割で見切り発車で進めるというものです。
上記の書籍では、要所要所で大幅な軌道修正リスクを排除する重要性についても述べられています。
2:8の法則は本書でも別の文脈で出てきます。
2:8の8のペースにもフォーカスした内容になっていますので、後ほど紹介します。
プロトタイプ(試作品)を作る
早く形にして出すことの重要性を本書で再認識しましたが、この「形にする」というのも重要だなと改めて感じました。
例えば「企画を考えて」と上司に言われた際に、アイデアを出して言葉で説明するだけでは不十分なケースがあります。
企画を形にする前に、「そもそもどういうものなのか想できない」とか「予算はあるのか」とか「商品になる保証はあるのか」とか、そういっことを言われて仕事を中断するのはもったいない話です。
イベントやプロジェクトの企画の場合、あらかじめこれらの不安を解消した、企画書が望ましいでしょう。
大事なのは形にすることです。
提案する相手が、同じ企画のゴールをイメージできるようにするためには、形にしたものがあったほうがスムーズに提案が通ります。
本書ではプロダクト開発を例に取り上げられていましたが、新製品のアイデアを思いつくことは、世の中を丁寧に見ている人には決して難しくないと述べられています。
難しいのは、そのアイデアを目に見えて触ることのできる、実際に動く物にしてしまう部分だと述べられています。
百聞は一見に如かずで、言葉で説明することが難しいときは形にて見せてしまうのが一番いいのです。
プロダクト開発だけではなく他の仕事にも通じる原理だと感じました。
仕事は最速で終わらせない
先ほど触れた2:8の法則について紹介します。
本書では2:8の法則で、最初の2割の期間でスタートダッシュにより仕事の8割を終わらせ、その後の8割を「流し」の期間としています。
この2割の期間でメインの仕事の残り2割と他のこまごました仕事を余裕を持って終わらせることを推奨しています。
ロケットスタートを推奨しておりラストスパート志向は種悪の根源としています。
そして私もやってしまいがちであった、スタートダッシュで仕事の8割が終わったからといって、そのままのスピードで仕事を終わらせることは推奨していません。
3日間頑張って完全に消耗した挙句、間断なく仕事を振られるようだったら3日目は休んでいたほうがましと述べられています。
私も経験上、スタートからゴールまで同じペースで仕事をしてしまったがために、間断なく仕事が振られ、たくさん抱えてしまうことが多くありました。
仕事を早く終わらせることよりも、仕事を安定して続けることを意識すべきです。
結果、焦って仕事をしていたときよりも早く、しかも高い完成度で終わるようになるのです。
個人的には経験上、仕事を抱えすぎにならないためにという点と、完成度を高める期間として、残り2割の仕事をする8割という期間は軽視すべきではないと感じました。
 バイプロLOG
バイプロLOG