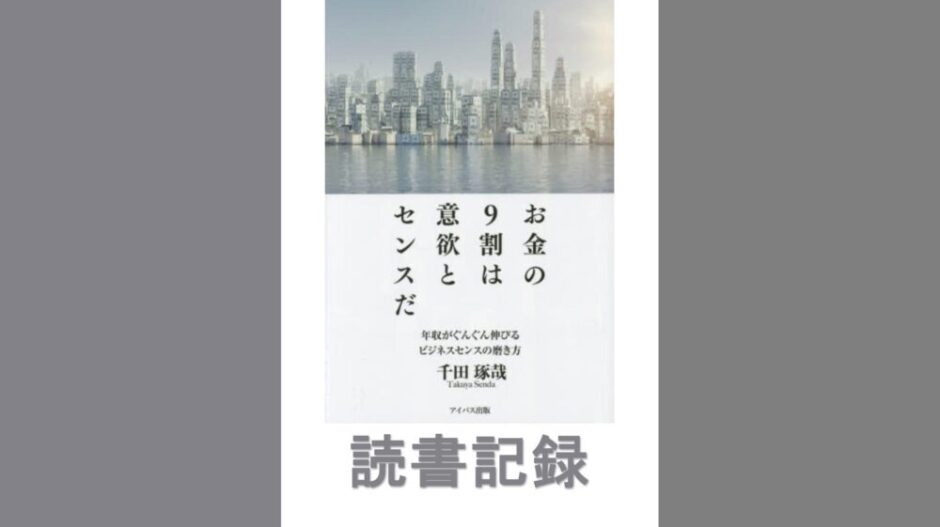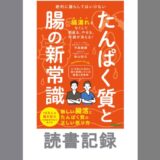Table of Contents
本を手に取ったきっかけ・感想
核心を突き、読者によっては目を逸らしたくなる現実をえぐるような文を書く著者ですが、個人的に好きな作家です。
凡人との行動特性の違いを知り、年収が伸びている人の行動特性を取り入れることで、ビジネスセンスを磨くために読みました。
今回は千田 琢哉さんの著書「お金の9割は意欲とセンスだ」を紹介します。
- 年収を上げたい人
- お金を稼ぐ人の習慣を取り入れたい人
人生に取り入れたい文脈
本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。
個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。
必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。
才能を世の中に還元する
本気で年収を増やしたければ、才能について考えることから逃げてはいけないと本書では述べられています。
この世の中は自分の才能をどれだけ活かせたかによって、収入が決まります。
本書では少しきつい表現になっていますし、それでも良いという人はいるとは思いますが、どんなに好きなことや楽しいことをやっていても、世間から評価されなければダメ人間はダメ人間のままだと述べられています。
もし、収入を上げたい、金銭的に生活を豊かにしたいという価値観を持っているならば、才能と向き合いそれを磨き続ける必要があります。
「評価される」ことに打ち込んでいると「楽しい」と一体化することもあります。
一方で、才能が厄介なのは、本人はごく当たり前にやっているから自分ではなかなか気づかないということです。
学校では苦労して磨き上げたことが才能だと思い込まされてきたというのも、才能に気づきづらくなっている一因かもしれません。
たいして苦労を感じなかったのに自然にできるようになったことや、他人と比較して苦労を感じていないことは何なのか、私達は自分の才能にもっと向き合い、個人としての才能を社会に還元することを考えなくてはなりません。
聞く力
本書では聞く力に関することも取り上げられていました。
相槌の打ち方を魅力的にすることは、お金や労力もかからない年収を上げていくための種まきになります。
あなたが話し終わって、「いい感じの人だったな」「もう一度会いたい」と思えるのはどんな人かを想像してみてください。
それはあなたの話を熱心に聞いてくれた相手であり、決して無理に話を聞かされた相手ではないはずです。
相槌をいかに上手に打つことができるかが年収を決めると言っても過言ではありません。
相手の話が自慢話だった場合、それを聞くのは、その時は確かに苦痛かもしれません。
ところが自慢話には相手の性格が見事に露呈されますし、貴重な情報が詰まっていることもあります。
神様は自慢話という形で、あなたにチャンスを運んできてくれているのだと考えましょう。
聞く力を鍛えることがなぜ年収を上げていくための種まきになるのか、本書では、相槌の打ち方が魅力的な人にはもっといい情報を話したくなるだろうと述べられています。
人はどうでもいい相手と魅力的な仕事をするよりは、大好きな相手とまあまあの仕事をする方を選びます。
経営者たちは経験上、どうでもいい相手と魅力的な仕事をしても、結果はまあまあに終わるのに対し、大好きな相手とまあまあの仕事をすれば、結果は魅力的に終わる可能性が高いことを知っています。
誰と仕事をするかということは、仕事の魅力度を少し下げてでも優先した方がいいというのは私も経験上実感していました。
素直
もしあなたが凡人だと自覚しているのであれば、とりあえず一度はやってみる癖をつけたほうがいいと本書では述べられています。
会社に入って、先輩や上司に指示されたことで、これ無駄なんじゃないかとか思うものもあるかもしれません。
しかし、一度やってみるのです。
やってみなければ分からなかったこと、見えなかったことというのは私の経験上も結構あります。
タイパに囚われすぎてはいけません。
とりあえず一度はやってみるものの、本当にあなたの性に合わなければ、二度目はやらなければいいのです。
性に合わないことは、一度どっぷり浸かってやってみれば十分にわかります。
一度やってみると、5年後や10年後に思わぬところで役立つ可能性だってあります。
どんなに無駄と思えることも、完璧に無駄になることなど一つもないのです。
自分が自然に続くことだけを継続する
著者が見てきた中では成功者たちは揃いも揃って飽き性だったとのことです。
しかし、矛盾することに、彼ら彼女らの継続力は半端ではなかったとのことです。
以下の書籍でも、億からの人になるためには習慣化する能力を身につけることがキーであると述べられています。
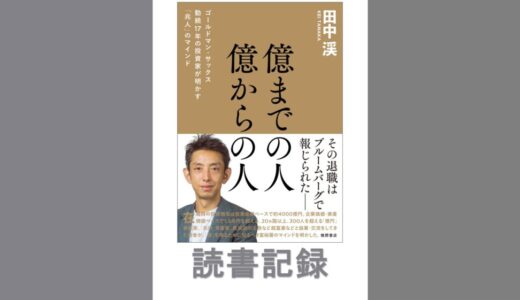 億までの人 億からの人|田中 渓 著
億までの人 億からの人|田中 渓 著
本書では、成功者たちは忍耐強く無理に物事を続けていたのではなく、自分が自然に続くことだけをやっていたのだと述べられています。
以下のような習慣化に関する書籍を読んだ私が付け加えるとすれば、自然に続くものを習慣化の対象に選んでいるというのもあるかもしれませんが、普通に生活していれば習慣化するのに抵抗が生まれるようなものを選んだとしても、それをうまく、抵抗感を感じない形で日常生活に取り入れ、仕組み化している面もあるのではないかと感じました。
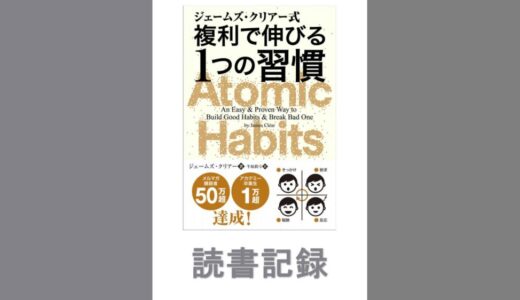 ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣|ジェームズ・クリアー 著
ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣|ジェームズ・クリアー 著
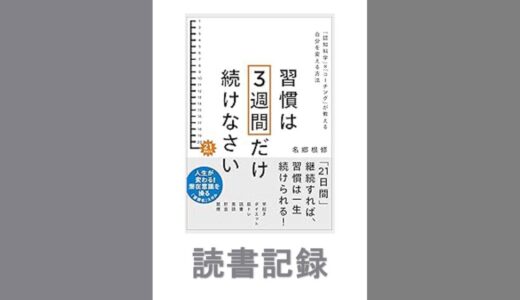 習慣は3週間だけ続けなさい|名郷根 修 著
習慣は3週間だけ続けなさい|名郷根 修 著
例えば以下の著者のように、 365日毎朝3時45分に起きて、「25km走る」「65km自転車に乗る」「7000m泳ぐ」というメニューのうち、どれかを毎日必ずこなすなんていう習慣は、明らかに習慣化しやすいものを選んでいると言うよりは、自然に続くように仕組み化した結果、今は抵抗感なくできているという状態ではないかと思うのです。
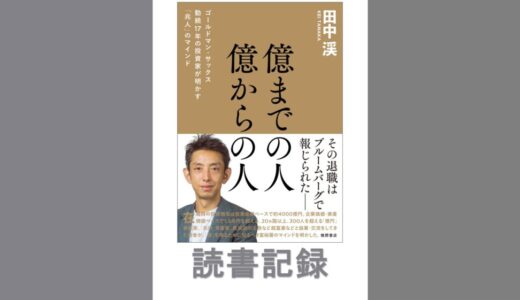 億までの人 億からの人|田中 渓 著
億までの人 億からの人|田中 渓 著
凡人と似て非なるのはこの継続する力です。
100にチャレンジして、1つでも継続できるものが見つかればそれで御の字と考えるのです。
その代わり、その1つに対しては常軌を逸するほどに人生を賭けていたようです。
「言われる前に」やる
もしあなたが将来月給50万以上の管理職や幹部社員を目指したいのであれば、「言われる前に」やることを本書ではおすすめしています。
上司やお客様に「これやって欲しいんだけど・・・・・・」と言われたら、できれば「終わりました」、最悪でも「ちょうど今、やっているところです」という状態でいるです。
「言われる前に」 やるためには、普段から上司やお客様を感動させるために動くことです。
相手を感動させるためには、常に相手の考えそうなことを先取りするのです。
 バイプロLOG
バイプロLOG